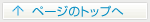Index
- ドクターインタビュー
- 第10回 自治医科大学 内科学講座血液学部門 教授 神田善伸先生
- 第9回 公益財団法人 ときわ会 常盤病院 院長 新村浩明先生
- 第8回 独立行政法人 国立病院機構 北海道がんセンター 名誉院長 西尾正道先生
- 第7回 公益法人がん研究会 がんプレシジョン医療研究センター 所長 中村祐輔 先生
- 第6回 公益財団法人 食の安全・安心財団 理事長 唐木英明先生
- 第5回 筑波大学 産婦人科学 医学博士 佐藤豊実先生
- 第4回 千葉労災病院 勤労者脊椎・腰痛センターセンター長 山縣正庸先生
- 第3回 HAB研究機構副理事長 寺岡慧
- 第2回 東海大学医学部消化器外科 中郡聡夫先生
- 第1回 HAB研究機構理事長 深尾立
第10回 自治医科大学 内科学講座血液学部門 教授 神田善伸先生
収録日:2019年11月2日
自治医科大学 内科学講座血液学部門 教授 神田善伸先生が白血病治療について語ります。
Part1:「白血病の種類と病態」
Part2:「慢性白血病の最新の治療(骨髄性・リンパ性)」
Part3:「急性白血病の最新の治療(骨髄性・リンパ性)」
Part4:「造血幹細胞移植」
Part5:「白血病治療の将来展望」
動画の要旨は以下になります。
■Part1:
「白血病の種類と病態」
血液の中には「赤血球」「白血球」「血小板」という大事な細胞があります。
赤血球は酸素を運ぶ役割、白血球はばい菌やウイルス等と戦って自分を守る役割をしています。血小板は出血したとき血を止める役割をしています。
その中の白血球ががん化して増殖してしまう病気が白血病です。
白血病には色々な種類があります。
白血球は骨髄性の細胞とリンパ性の細胞に分かれますから、骨髄性の細胞ががん化したら骨髄性白血病、リンパ性の白血球ががん化したらリンパ性白血病ということになります。
また、病気の発症の仕方として急性と慢性があります。
・急性白血病
白血病の中でも急性では、幼弱な細胞と呼ばれるまだ育っていない白血球が、がん化し急激に増えるため、正常な白血球・赤血球・血小板が全く作れなくなってしまうのです。白血球が無くなれば感染症を起こして発熱し、赤血球が無くなれば酸素が運べなくなり息切れや動悸やだすさなどの貧血症状がでます。血小板がなくなると出血症状が出ます。これが急性白血病です。
・慢性白血病
慢性では比較的緩やかで、正常な白血球・赤血球・血小板の働きが維持されているので、激しい症状は出にくいです。健康診断で「白血球が多いですよ」と言われて来られたり、ちょっとだるさがあるとかお腹がはっているという症状で来られる方も多いです。
このように白血病はまず急性か慢性で分かれて、さらに骨髄性かリンパ性かで分かれて、2×2=4で4通りあります。急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病というように、4通りあるわけです。
■Part2:
「慢性白血病の最新の治療(骨髄性・リンパ性)」
・慢性骨髄性白血病
慢性骨髄性白血病の治療はこの20年間で大きく変わりました。
1990年代までは骨髄移植をしないと治らない病気だったのですが、今は飲み薬だけでほぼ治るに近い状態まできています。
例えば、慢性白血病は、9番目の染色体と22番目の染色体が入れ替わるという遺伝子異常によって起きていますが、その遺伝子異常のところを狙い撃ちする薬「チロシンキナーゼ阻害薬」という特殊なお薬が開発されまして、それを飲み続けることによって、ほとんどの方が病気を気にせずに暮らしていけるというところまできています。
さらに最近分かってきたことは、良い状態をある程度の期間続けているとその薬をやめても再発しない人が一定数いるということです。慢性骨髄性白血病に関してはかなり治療が進歩しています。
・慢性リンパ性白血病
慢性リンパ性の白血病は日本人には少ない病気です。この病気の場合、症状が軽ければ治療しないで様子を見るという選択肢もありますが、いつかは進行してきて白血球が急増したりリンパ節が腫れるという症状が出てくるので、そうなったら抗がん剤治療になります。通常は点滴の治療から始めます。
通常の抗がん剤を続けているとだんだん効かなくなってきますが、慢性リンパ性白血病でも新しい薬が開発されてきて、その新薬を使うとかなり良い状態が長く維持されるという方も増えてきています。
■Part3:
「急性白血病の最新の治療(骨髄性・リンパ性)」
急性白血病は、ご本人に何かしら症状が出て受診される方がほとんどです。治療も急いで始めることになります。
通常、入院されて骨髄検査をし診断をつけて、もう翌日から治療を始めるという、そいう流れになります。
白血病というのはもともと全身に広がっていますので、手術で切り取ったり放射線を当てて治療するということができません。その代わり、肺がんや胃がんなど他のがんに比べて抗がん剤が良く効きます。急性白血病の治療も抗がん剤が中心になります。
治療では、2つ以上の複数の抗がん剤を併用した化学療法というものをやります。
お薬の内容は、骨髄性とリンパ性で少し違いがありますが方向性としては同じで、骨髄性であってもリンパ性であっても複数の抗がん剤を使って、まず完全寛解という状態を目指します。
完全寛解というのは、骨髄検査をしてもほとんど正常で、普通の血液検査してもほぼ正常、ほとんど正常と変わらない状態のことをいいますが、これは完全に治った状態の根治とは違います。
完全寛解に入ってもまだ体の中には白血病細胞がたくさん残っているというのが通常です。完全寛解になっても
抗がん剤治療を何回か繰り返して治すことを目指していくという流れになります。
■Part4:
「造血幹細胞移植」
慢性骨髄性白血病に関しては、ほとんどの方が治る(厳密な意味では完治ではなく治ったに近い状態)ようになっています。急性白血病についても、何割かの方は化学療法だけで治るというところまできています。
しかし、残念ながらまだ化学療法が効かない、いったん効いてもまた再発してしまうという方がいます。
そういう方には造血幹細胞移植という治療法が必要になってくるわけです。
造血幹細胞というのは、白血球・赤血球・血小板のすべてのもとになる細胞です。
「幹」という文字があるように、木の幹から全ての枝に分かれていくというイメージの細胞です。
自分自身を増殖する力があるので、幹細胞さえ入れてあげればそこから白血球・赤血球・血小板が全部できてくる、そういう細胞を造血幹細胞と呼んでいます。
通常は骨髄の中にあるのですが特殊な薬を使えば血液中にも出てきますし、赤ちゃんのへその緒、臍帯血にも幹細胞がたくさんあります。
造血細胞移植には、骨髄を移植する方法と末梢血を移植する方法と臍帯血を移植する方法の3つがあります。
・なぜ造血細胞を移植するのか
白血病には抗がん剤がよく効くので、より強い抗がん剤を使えばより効果が得られるのですが、抗がん剤をどんどん増やしていくと、正常な白血球や赤血球、血小板を作る骨髄細胞がダメになってしまいます。だから一定以上は抗がん剤を増やすことができません。
ところが、健康な造血幹細胞を移植すればそこから血液を作ってくれますから、通常はできないよう強力な抗がん剤治療ができるようになるのです。
それが造血幹細胞移植の目的です。
・造血幹細胞移植の拒絶反応
白血病の場合、通常他人の造血幹細胞を移植しますが、その際免疫反応が起きます。
白血球は自分自身の体を守るためにばい菌やウイルスを攻撃しますが、他人の細胞も攻撃してしまいます。例えば他人の腎臓や肝臓を移植するとそれを攻撃してしまう、いわゆる拒絶反応が起きます。
造血幹細胞移植の拒絶反応の場合は少し複雑です。
造血幹細胞を移植すると拒絶反応が起きますが、白血病では移植する前に強い抗がん剤治療しているため患者さんの免疫力が弱まっており拒絶反応で造血幹細胞がはじかれてしまうことはありません。ドナーさんの幹細胞は患者さんの体の中に住み着きます(生着)。
しかし、今度は逆の免疫反応が起きるのです。
患者さんの体に入ってきたドナーさんの白血球の立場からすると周囲がすべて他人の細胞のわけです。そこで周りの内臓、皮膚、肝臓、腸などを攻撃する免疫反応が起きてしまいます。
専門用語で「GVHD(graft versus host disease/移植片対宿主病)」と呼ばれる、このGVHDが一番厄介な副作用です。
GVHDを抑えるために免疫抑制剤を使いますが、今度は感染症を起こしやすくなってしまいます。
そういった非常に難しい治療です。
しかしこの治療法によって通常の化学療法では治らない白血病患者を治せるようになってきました。
全員を治せるわけではありませんが、これまで救えなかった一部の患者さんを治せるようになってきた、そういう治療法です。
化学療法も進歩してきたように幹細胞移植も進歩してきています。
以前は、例えば50歳くらいまでしか移植できなかったのが70歳くらいの方まで移植できるようになっていますし、以前はHLA(Human Leukocyte Antige/ヒト白血球型抗原)型がピッタリ一致してないと移植できなかったのが、今は少しズレていても移植ができるようになっています。そんな風に進歩してきています。
■Part5:
「白血病治療の将来展望」
新薬のほか、最近は免疫を活かした新しい治療法も次々と開発されていっています。
例えば白血球の中のT細胞を利用した治療法です。
T細胞というのはリンパ球の一種で、がんをやっつける力がすごく強いのですが、そのT細胞をうまく利用した白血病の治療法が、実際の診療現場にも使われるようになってきました。一般の抗がん剤が全く効かなかったような患者さんでもその治療で寛解に入ったりするようなことが起きてきています。
ただやはり独特な副作用があり、免疫反応で色々な症状が全身に出ることもありますし、また5年10年と治療効果が維持されるのかまだわかっていないところもあります。
また、やはり高額な治療費の問題があります。
日本の医療制度は素晴らしく、患者さんご自身の負担は高額療養費制度によって抑えることができるので、診療現場ではそれほど問題にはなっていませんが、一度の治療費には実際に数千万円かかることもあるので、日本のこの皆保険制度が今後もこういった治療費に耐えられるのか、一つの心配ごとではあります。
第9回 公益財団法人 ときわ会 常盤病院 院長 新村浩明先生
収録日:2019年6月22日
公益財団法人 ときわ会 常盤病院 院長 新村浩明先生が前立腺がんについて語ります。
Part1:「前立腺がんの疫学」
Part2:「前立腺がんの検査」
Part3:「治療法の選択」
Part4:「最新の前立腺がん治療と将来展望」
動画の要旨は以下になります。
■Part1:
「前立腺がんの疫学」
この20年で前立腺がんの罹患率は統計的に増加しました。
理由としてひとつには、PSA検査という腫瘍マーカー検査が普及したことがあげられます。採血で簡単に検査できるため検診にも組み込まれ、前立腺がんの早期発見につながりました。以前なら前立腺がんと診断されないまま亡くなったようなケースでも早期に見つかるようになったので、2000年初頭から羅漢率が増えてきています。
もう一つの理由としては食生活の欧米化があります。
前立腺がんは50代から見つかり始めて、60~80代と年齢が進むにつれて増加します。ピークの70~80代で見つかることが多いのですが、実は若い頃に既にがんが発生しており非常にゆっくりと成長、50代以降に発見される、ということも多いのではないかと言われています。
■Part2:
「前立腺がんの検査」
ほとんどの場合、早期の前立腺がんには症状がありません。進行すると前立腺が腫れあがり排尿障害になったりしますが、早期にはそのような症状はないのが普通です。
現在の前立腺がんの検査では、前立腺特異抗原=PSA(prostate-specific antigen)の血液検査で早ければ当日にわかります。
基本的にはPSA値が4.0ng/ml以下の場合は正常ですが、4.0ng/mlより高値の場合前立腺がんの疑いが出てきます。
PSAで異常値が出た場合、次は画像診断になります。
MRI検査で画像診断をし前立腺に異常があった場合は、針生検で確定診断となります。針を刺して実際に前立腺組織を採取します。採取した組織にがん細胞があれば前立腺がんという診断がつきます。
家族性に前立腺がんが発生することはよく知られています。
もし親兄弟が前立腺がんに罹患していたら、なるべくまめにPSA検査を受けることが重要です。
予防となると、前立腺がんの予防は非常に難しいです。
がんの予防はがん免疫が非常に関わってくるので、食生活やストレスの無い生活、適度な運動など、基本的に健康的な生活をして免疫力を向上させることが非常に大事になってきます。
■Part3:
「治療法の選択」
前立腺がんの大きな特徴として、男性ホルモンがないと増殖しないということがあります。その特徴を利用したホルモン療法という薬物療法があることが、がん治療としては非常に特殊です。男性ホルモンをブロックする注射薬や経口薬があり、そういう薬物療法だけで前立腺がんが小さくなったり、時には消えてしまうこともあります。
しかしがんの増殖を止める治療法なので生涯にわたってホルモン療法を続けなければならず、長期間男性ホルモンが無い状態にすることで、骨粗しょう症が起きやすくなるという大きな問題があります。骨粗しょう症の治療薬と組み合わせてホルモン治療をするのもいいですが、まだ若い患者の限局された前立腺がんならば、2つの方法、手術か放射線で治す方法があります。
前立腺がんは、早期発見なら9割以上の方は完全に治ってしまうがんです。
早期がんでも微小な転移があり、手術また放射線治療で根治まで至らないケースであっても、ホルモン療法というバックアップの治療法があるので他のがんに比べると治療法の選択肢が幅広いがんです。
手術療法も以前は開腹手術で出血量も多く非常に難しい手術でしたが、現在はダヴィンチシステムと言われるロボット手術が普及しています。これは傷も小さく手術時間も短く出血量も少ないという非常に理想的な手術で、合併症も必要最小限に抑えられています。
前立腺がんの手術の流れは、
(1)検診や人間ドックで検査でPSA検査(採血)
(2)PSAの数値が高ければ組織検査(針生検)
(3)がん細胞が見つかれば、転移の有無を調べる(CTや骨シンチグラムなど)
(4)転移のない限局がん→手術療法または放射線療法
となります。
主治医が相談して手術療法が選択された場合の入院の流れは
(5)外来で手術の予約
(6)手術の前日または前々日くらいから入院
(7)手術当日は全身麻酔。手術は約3時間(長くても4~5時間)
(8)一週間の入院(手術の翌日から歩いたり食事をしたりできる)
(9)手術後一週間目に尿道カテーテルを抜く
となります。
アメリカだと手術の翌日や翌々日に退院になるほど傷が小さく、退院するころには普通に日常生活が送れる状態になっています。カテーテルを抜いてすぐは少し尿失禁がありますが、尿漏れパッドを着けていれば仕事にも復帰できるでしょう。
■Part4:
「最新の前立腺がん治療と将来展望」
最新といっても治療法は主に2つ、手術による切除または放射線治療の二大根治療法になります。
手術自体はダヴィンチシステムというロボット手術が現在のスタンダードになってきています。
放射線治療では複数の方法が選択可能で、例えば放射線を多方向から効率的に照射し合併症を少なくする3Dとか、陽子線治療、重粒子線治療など、色々です。
ただ、例えばリンパに転移している場合、手術療法ならリンパ節郭清を追加ですることができるのに対し、局所にだけ当てる放射線療法だとリンパ節にかけることはしないので(標準的には)、もしリンパ節に転移がありそうなら手術療法を選ぶのもいいでしょう。
ただ、基本的に手術療法も放射線療法も、再発率は変わらないといわれています。
体力があり、がんは全部取り除きたいという場合は手術を選び、心臓が悪かったり重い糖尿病だったりして手術が難しいなら放射線療法を選ぶという判断もあるでしょう。
前立腺がんは男性にとって非常に罹患率の高いがんですが、全てが生命に関わるがんかというと疑問です。
その証拠に、亡くなってから前立腺がんが見つかるという報告は以前から多いのです。前立腺がんが非常にゆっくり進行したために、治療しなくても寿命を全うされたということです。
医師や患者さんにとって一番の問題は、その前立腺がんを治療すべきかどうか、はっきりとしたマーカーが無いことです。遺伝子学的な何かマーカーが見つかれば、治療が必要な前立腺がんはしっかり治療、不必要なら治療はしないという方法がとれるのではないかと思っています。
第8回 独立行政法人 国立病院機構 北海道がんセンター 名誉院長 西尾正道先生
収録日:2019年6月22日
独立行政法人 国立病院機構 北海道がんセンター 名誉院長 西尾正道先生が放射線治療について語ります。
Part1:「放射線とは」
Part2:「放射線の医療への応用」
Part3:「放射線療法が得意な癌(がん)種は?」
Part4:「最新の放射線と将来展望」
動画の要旨は以下になります。
■Part1:
「放射線とは」
「放射線」というのは広い意味では電磁波です。波長を持った電磁波の総称です。
ただし一般的には放射線は狭い意味で使われ、紫外線より短い波長を持った、人体に影響のあるものを放射線と呼びます。
波長には長いものから短いものまであります。
赤外線と紫外線の間の可視できる長さの波長が虹です。虹は人間に見える唯一の放射線です。
波長の長いもの、電子レンジのマイクロ波やラジオ波などは人体を突き抜ける力はありませんが、波長の短いものは物を突き抜ける力があります。
例えば、紫外線の短い波長は毒性を持ち、DNAを傷つけるなどの害をもたらします。そのため紫外線に当たりすぎると皮膚がんになる危険がありますが、紫外線程度の波長なら体の奥まで入ることはなく、皮膚だけにしか当たりません。しかしもっと波長が短くなれば体を突き抜ける力を持つわけです。
つまり、人体に悪い影響を及ぼすもの、紫外線より短い波長の電磁波を、いわゆる「放射線」と言っているわけです。
その他の放射線としては、微粒子として飛んでるようなものもあります。またアルファ線とかベータ線というような放射線もあります。
1895年レントゲン博士が、蛍光を発する何か未知のもの、X線を発見しました。得体の知れない光線だからX線と名付けたわけです。
翌年の1896年には、自然界の鉱物から放射線(アルファ線)が発見されるなど、放射線の研究はどんどん進歩し今に至っています。
■Part2:
「放射線の医療への応用」
放射線療法は、診断学から始まっています。
1895年11月、レントゲン博士がX線を発見し、2か月後に公表された妻の手のX線写真が世界で最初のレントゲン写真になりました。
レントゲン写真では、放射線を当てて突き抜けた放射線がフィルムに当たり、それを現像します。透過と吸収の関係で、骨の部分は放射線が吸収されて出てくる量が少なく、肺は空気しかないので突き抜ける放射線の量が多いわけです。放射線の突き抜ける量で白黒の濃淡の違いができ、一つの画像になります。
ラジウムを発見したキュリー夫人は、第一次世界大戦の時に、バスにレントゲンの発生装置を積んで戦地を回りました。レントゲン写真を撮れば体に入った砲弾がわかるので治療の助けになったのです。キュリー夫人はそういう活動もしていました。
放射線治療では、放射線は体に害がある(肌にあてるとただれる)ということは、逆にその力ががん治療に使えるのではないか、そういうことから始まっているわけです。
ところが、昔はエネルギーが低かったために皮膚直下までしか当たらず奥まで届かなかったのです。
しかし、アメリカの物理学者で電話の発明をしたグラハム・ベルは、放射線を出す物をがんの患部に直接埋め込んだらいいのではないかと提案しました。今でいう小線源治療というものです。例えば、放射線を出す物質を病巣に貼り付ければ、そこだけ放射線が当たるわけです。つまり内部被ばくを利用した治療です。
1920~30年代は、例えば子宮がんなどは当時まだ危険な手術でした。そこで膣と子宮に線源を入れる小線源治療を施したら、結果的に外科治療成績より良くなったのです。それで一気に小線源治療というものも普及しだしました。
その過程でも物理工学はどんどん進歩し、エネルギーの高い放射線が出せるようになってきました。
胸部レントゲン写真を撮る時のエネルギーは100キロ エレクトロンボルトくらいですが、その10倍のメガ エレクトロンボルトという高い放射線がでるようになっています。電子の加速の程度が強く、深くまで通るエネルギーの高い放射線が出るリニアックという機械もできました。リニアックは直線加速器という機械で、深いところまで比較的効率よく飛ぶ放射線で治療できます。
診断学の歴史で画期的なことといえば1974年です。まだ50年も経っていないですね。イギリスのEMI社からCTが出ました。ハウンスフィールドという学者によって発明されましたが、発明の数年後という異例の速さでノーベル賞を受賞しました。CTはそれほど画期的な技術進歩だったわけです。
それまで放射線の画像診断はアナログの世界でした。フィルムに当たった放射線の量をアナログの写真で見ていたのです。
CTはフィルムに当たった量をデジタル化した数値で受け取って、そのデジタル値を白黒の濃淡の画像に構築するというもので、医療のデジタル化の出発点になったとも言えます。それによってより緻密な画像が得られるようになりました。
そこからすごいスピードで技術は進み、パソコンやIT技術が医療の世界に入り込んで、加速度的に進歩したのが放射線の診断や治療の歴史です。
■Part3:
「放射線療法が得意な癌(がん)種は?」
放射線治療の効果が高いのは、放射線の感受性(放射線の効き具合)が高いがんになります。感受性が高いのは、抗がん剤もそうですが、細胞分裂が盛んなところという特徴があります。成長期の子どもが放射線の影響を受けやすいのはそのためです。
いずれにしても治そうとするなら、適量の放射線をかけなければいけません。
ですから、物理工学の歴史では、病巣にだけ集中して照射させる方法や、必要な放射線量などの研究がこの100年間ずっと続いているわけです。
◇放射線の感受性(放射線の効き具合)が高い組織、がん
・骨髄(造血組織)
骨髄にある造血幹細胞は盛んに分裂しながら、各種血液細胞に分化していますから、放射線感受性は極めて高く、骨髄に放射線がたくさん当たると白血球の減少などの影響が出ます。
・腸管
腸管も細胞分裂が盛んです。小腸の上皮細胞は2~3日で入れ替わっています。だから下痢をしても上皮が入れ替わり、2~3日で治ってしまう。それほど細胞分裂が盛んで、放射線の感受性も高いのです。放射線を全身に浴びたなら、まず最初に損傷するのが腸管です。下痢や脱水で電解質バランスや水分バランスが崩れてしまいます。
腸の周辺の臓器に放射線を照射する時は、腸に放射線が多く当たらないようにする必要があります。
・悪性リンパ腫
悪性リンパ腫は、主にリンパ節、脾臓および扁桃腺など感受性の高いリンパ組織に発生します。感受性の高い臓器からでた悪性リンパ腫も感受性が高いわけです。
正常なリンパ球同様、悪性リンパ腫も放射線に対して弱く、治療ではかける放射線量も少なくて済みます。
・扁平上皮がん
がんの7割を占める腺がんです。
放射線をかけすぎると障害が出てしまうので、治るか治らないかの一歩手前くらいで調整をします。
◇手術と組み合わせた放射線療法
術前照射と術後照射を使えば、目一杯かける必要のない量で済むので、あまり障害を起こさないという利点があります。
・術前照射
大きながんを放射線で小さくしてから手術しやすくするのが目的なので、放射線をめいっぱいかける必要はありません。
・術後照射
手術で取り残したがんを死滅させるためにかけます。例えば、乳がんの場合、まずしこりだけを取り除き、パラパラと周囲に残っているがんに放射線をかけます。乳房の原発巣を放射線だけで治そうとすれば大量の放射線をかけることになり、後の引きつりの原因にもなります。メインの腫瘍だけは手術で取り除き、パラパラ残っている場合は、7~8割くらいの放射線量でコントロールしながら術後照射する、というのが現在のスタンダードな乳がんの治療法になります。
◇緩和医療としての放射線
骨転移がんなど、骨転移による痛みを軽減する目的の緩和照射です。放射線をかけることで痛みはほぼ確実に取れます。照射線量も少ないため後遺症がでる心配がありません。また、放射線をかけたところは仮骨化してきます。骨が溶ける溶骨性の骨転移では、背骨などの骨に転移し圧迫骨折すると神経を傷めて麻痺になることもあるので、放射線で痛みを取り仮骨化させて骨もつくることは重要です。
このような緩和医療で放射線を利用するなど、病態に応じて上手に使えば有効な方法があるわけです。
■Part4:
「最新の放射線と将来展望」
物理工学は大変進歩しました。例えば、昔のリニアックでは、放射線をかけたくない場所にシャドウトレイという鉛の板を手作業で置いて放射線をブロックしていたものです。ところが今は2.5ミリぐらいの細い鉛の板が機械に組み込まれていて、コンピューター制御で開閉できるようになっています。
最新の治療法としては以下のものがあります。
・陽子線治療と重粒子線治療
腫瘍にだけ放射線を当て、周囲の正常細胞へのダメージを抑える線量分布というかけ方ができる放射線治療のひとつです。放射線治療としては理想的な方法ですが、非常に高額な機械です。
・リニアック(直線加速器)
X線治療装置としては、リニアックと呼ばれる装置が一般的です。
リニアックは放射線治療装置の中で最も普及した装置です。
・強度変調放射線治療(IMRT)
病巣が変形している場合、周囲の正常組織や臓器にも放射線が当たってしまう問題がありました。この強度変調放射線治療では専用のコンピュータを用いてX線を多方向から変形させながら照射することができます。これにより周りの正常組織への損傷を避け合併症を低く抑えることが可能になりました。日本では今、300か所くらいの施設で利用できます。今の主流になっています。
・画像誘導放射線治療(IGRT)
例えば肺がんの腫瘍は呼吸に伴って移動します(呼吸性移動)。
画像誘導放射線治療では、2方向からのX線透視で病巣を確認しながら、ターゲットを追跡して放射線を照射するので、動いている範囲全体に当てる必要がなくなります。正常細胞を傷つけず病巣に集中して放射線をかけることができます。
このように、照射するたびに画像で位置を確認し、動くような病巣があればそれも追尾、動体追跡して照射するということが機械でできます。これからさらに普及していくと思われる注目の治療法です。
・ペンシル ビーム スキャニング(PBS)
非常に小さいビームを、効きにくく治りにくい腫瘍に集中してかける方法です。幅の狭い陽子線ビームで塗りつぶすように腫瘍に照射します。
これにより、感受性の強弱に応じて腫瘍の中で放射線量を調整するという、言うなれば“腫瘍内強度変調放射線治療”というようなことが、将来コンピューター制御などで可能になるでしょう。
基本的に、放射線治療というのは「切らないで治せる治療」ですから、機能と形態を全くそのまま温存できるわけです。
そういう点では、同じがん治療でも、切らないで済むのなら切らない治療で、放射線治療を上手に選択してほしいと思います。
第7回 公益法人がん研究会 がんプレシジョン医療研究センター 所長 中村祐輔 先生
収録日:2019年6月22日
公益法人がん研究会 がんプレシジョン医療研究センター 所長 中村祐輔 先生がプレシジジョン医療について語ります。
Part1:「プレシジョン医療とは」
Part2:「診断法の現状と遺伝子検査」
Part3:「治療法の現状と分子標的薬の進歩」
Part4:「ネオアンチゲンと免疫療法」
Part5:「わが国の現状」
動画の要旨は以下になります。
■Part1:
「プレシジョン医療とは」
日本人には馴染みのない言葉ですが、オバマ前大統領が2015年の一般教書演説で「プレシジョン医療(プレシジョン・メディシン)」を推進していくことを発表してから一気に広まりました。「いつでもどこでも、あなたにピッタリ合った医療を提供しましょう」という意味です。
プレシジョンは英語で「精密に」「正確に」という意味で「精密医療」と訳されることも多いですが、私自身は20年以上前から「オーダーメイド医療」という言葉を提唱しています。
例えば、ABOの血液型を判定せずに輸血することなど無いように、病気の性質、患者さんの性質あるいは個性を明らかにし「正確に病状を知った上で、その人にぴったりした医療を提供しよう」という概念がプレシジョン医療です。
■Part2:
「診断法の現状と遺伝子検査」
病気の特徴を調べる検査は、例えば血液検査、画像診断、超音波などいくつも種類がありますが、中でも遺伝子の研究分野は急速に進んできました。
遺伝子を調べるコストにしても、2001年は100万の遺伝暗号を調べるのに100万円かかっていましたが、今は1円でできるのです。100万分の1にコストが下がったわけです。
患者さんの遺伝子を調べるのに一千万円かかるとしたら医療現場では使えませんが、今は手に届く範囲で遺伝子検査ができるようになりました。
しかも個別の遺伝子だけでなく、遺伝子全体を調べることも可能になってきたのです。
がんのように遺伝子の異常が原因で起きる病気も、遺伝子を詳細に調べて患者さん自身の個性がわかるようになってきました。今はがんの診療に遺伝子検査は欠かせません。
他にも、例えば糖尿病を例にとってみると、尿に糖が混ざる病気を糖尿病と呼んでいますが、病気を起こす仕組みは様々です。インスリンが作られなくなったのか、インスリンは作られているけれども出せなくなったのか、インスリンは出ているけれども反応が悪くなったのか、色々な原因があり、それを明らかにした上で治療をしていきます。
様々な種類の検査がある中でも遺伝子検査は、コストが下がり早く正確にできるようになったために医療現場に広がってきています。
■Part3:
「治療法の現状と分子標的薬の進歩」
がんの場合、今まではどの臓器の場所で、肺がん乳がん胃がんなどと判別され治療法が決められてきました。その後、顕微鏡でみるようになり、例えば肺がんでも小細胞がん、扁平上皮がん、腺がんと分類されるようになりました。
しかし今はもうそのような分類ではなく、遺伝子検査によってその人に合った薬が使われるようになってきたわけです。がんの分野では、遺伝子検査でがんを分類し遺伝子の分類で薬を提供するようになってきました。
また、薬疹とよばれる皮膚のアレルギー症状が出現することがありますが、それも15年前までは、特異体質だとされてきました。私たちは、家系や体質で親から受け継いだものだと漠然と理解していましたが、今では特定の遺伝子型に反応することがわかってきています。
例えば、薬のアレルギーで起きるその薬疹は、薬剤とHLA分子(白血球の型)の組み合わせで起きる特異な反応だとわかり、台湾では今、遺伝子検査をしないと薬が処方されないというところまできています。
そういう意味では、日本は少し遅れている感はありますが、遺伝子をキーワードに、医療の分野が大きく変わろうとしていると言っても過言ではないと思います。
20世紀に登場した抗がん剤はこれまでがん治療に使われてきましたが、がん細胞だけでなく正常な細胞にまでダメージを与えてしまいました。
分子標的治療薬というのは、原因だけを攻撃するような形で生み出されました。がん細胞だけを狙い撃ちできる治療薬です。
例えば肺がんだと、日本人の4割くらいにその人にあった分子治療薬を開発・投与することができます。
敵を知る、敵をちゃんと認識した上で攻撃するという形で治療薬が変わってきたわけです。それが分子標的治療薬です。
■Part4:
「ネオアンチゲンと免疫療法」
免疫療法でおそらく一番有名なのは、2018年のノーベル賞に選ばれた本庶佑先生が、免疫療法のもととなるような分子を見つけられたことでしょう。
本庶先生が見つけられた分子というのは、がんが自分の身を守るために作っている物質を抑え込むような働きがあるのです。
そのような新しい免疫チェックポイント抗体は、がん細胞を直接攻撃しているわけではないことが重要です。
免疫の力を抑えてがん細胞を守っている免疫チェックポイント分子という分子を、免疫チェックポイント抗体(阻害薬)でブロックし、がん細胞を攻撃する免疫の力を高め、それによりがん細胞をやっつけるわけです。
非常に重要なのは、これまでのがん治療は三大療法の「外科療法」「化学療法(抗がん剤)」「放射線療法」だったのが、今では「免疫療法」という新しい分野が科学的に証明されたことです。
遺伝子解析技術によって、その新しい免疫チェックポイント抗体がなぜ効くのか、を調べている過程で、患者さん自身のリンパ球が、がん細胞の表面にある目印=ネオアンチゲンを見つけてがんを殺しているということがわかってきて、科学的にも証明されたわけです。
一方、がん細胞の目印(がん抗原)=ネオアンチゲンに対するリンパ球の働きを逆手にとって、がん細胞の目印をうまく使えば、患者さん自身の免疫力をもっと高めることができるのではないか、ということから、今や、アメリカや中国でネオアンチゲンを使った免疫療法の動きが始まっているわけです。
■Part5:
「わが国の現状」
わかりやすく言えば、日本は一周どころか数周遅れているような状況ですね
やはり、免疫療法にはマイナスのイメージが長い間あったので、今アメリカや中国で行われているようなことまで、まともに評価できないような風潮になってしまっています。
科学の進歩は今までの概念を変えつつありますけれども、科学的な理解に基づいて次の手をどう打つべきなのかを考えるべきだったのが遅れてしまいました。
過去には遺伝子研究など役に立たないという方もいて、その方に強い影響力があったものですから、日本の遺伝子研究が一気に遅れてしまい、結局、遺伝子の遅れだけではなく免疫療法や新しい分野の遅れにもつながってしまったのです。
これはもう国を挙げて、10年後20年後の医療を見据えて対策をしていかなければならないでしょう。特にがんの場合、科学的に客観的に冷静に評価してこの分野を推進していく必要があると思います。
ここではネオアンチゲン療法の話をしてきましたが、つい最近、1回3千何百万円という、免疫療法の一種である治療法が承認されました(スイス製薬大手ノバルティスの遺伝子治療薬「キムリア」2019年3月に承認。投与1回あたり3349万3407円)。
CAR-T細胞療法といって、患者さん自身のリンパ球にあるT細胞(がんを攻撃する)を取り出して、遺伝子医療技術で改変し、CAR(キメラ抗原受容体)と呼ばれる特殊なたんぱく質(がん抗原を特異的に認識できる)を作り出せるようにします。CARを作り出すことができるようになったT細胞をCAR-T細胞と呼びます。このCAR-T細胞を患者さんの体に再び戻すという、がんの治療法です。
非常に高額な治療法ですが、新しい免疫療法として認められました。
このように、免疫が治療に非常に重要だということが科学的に証明されてきたので、これから10年間くらいは、様々な種類の免疫療法が出てくると思います。
日本は、その免疫療法、患者さんの免疫の重要性を認識して手を打たない限り、世界からもっと遅れてしまうかもしれません。
今でも、新しい治療法を求めてアメリカに行く方は少なくありませんが、このまま日本が何も手を打たないと、日本の患者さんが治療のために中国に行くという状況になるかもしれません。
それを誰がどう認識してどんな手を打つか、ということです。
私ももちろん情報を発信していきますが、やはり患者さんと一体となって新しい医療を探っていくという、そういうことが非常に重要ではないかと思います。
第6回 公益財団法人 食の安全・安心財団 理事長 唐木英明先生
収録日:2018年10月6日
公益財団法人 食の安全・安心財団 理事長 唐木英明先生が健康食品について語ります。
Part1:「健康食品の呼称の違いについて」「健康食品の効果や安全性」
Part2:「摂取する時や表示に関する注意点」「病後に健康食品は摂っていいのか」
Part3:「海外の健康食品の安全性」「健康食品の可能性」
※動画左上のメニューボタンをクリックすると、再生する動画を選択することが出来ます。
各動画の要旨は以下になります。
■Part1:
「健康食品の呼称の違いについて」
健康食品とサプリというのは、ほとんど同じ意味で使われています。
日本では健康食品と言われており、海外、アメリカやヨーロッパではサプリメントと言われております。日本では略してサプリと言われていますが、これらは同じものを指しています。
ただし、健康食品は、狭い意味での健康食品といわゆる健康食品の2つに分けることができます。
本当の意味での健康食品とは、特定保健用食品と言われるトクホ、機能性表示食品、そして栄養機能食品、この3種類があります。これは、いわゆる健康食品と何が違うかというと、狭い意味での健康食品は、効能と安全性についての科学的な根拠があるもので、いわゆる健康食品ははないもの、というように2つに分かれます。
皆様には健康食品を選ぶときにはトクホか機能性表示食品を選んでほしいと思います。
栄養機能食品というのはビタミンとミネラルが含まれていますが、そういった表示のあるものを選んでほしいと思います。
「健康食品の効果や安全性」
安全性は一番大事です。安全性については、トクホは企業がその製品を使って臨床試験をやり、その臨床試験の結果をに提出をします。国の審査会がその内容を審査してそして安全性が認められれば、これはトクホとして認可されるということになります。
機能性表示食品は、企業がその根拠となる論文を集めて、その論文を消費者庁に提出をします。そして届け出でをすることで認可になります。
つまり、トクホの方は国の審査がありますが、機能性表示食品は国の審査がないということになります。代わりに消費者庁は届け出でがあった処理を全部ホームページで公表しています。そのホームページを見て、誰でもが安全性について確認ができるという精度です。
トクホは国が審査し、機能性表示食品は国民のみなさんが審査するという違いがありますが、科学的な根拠があるという意味では両方とも安全性は担保されているというふうに考えて良いと思います。
トクホの方は最終製品で人を集めて臨床試験をしなくてはいけないのですが、これはかなりのお金と時間がかかります。
ただ機能表示食品の方は、既存の論文を集めるだけですのでかなり簡便にしんせいすることができます。
トクホの制度ができた時には、国は大変期待をしてトクホが広がればいわゆる健康食品という何の科学的根拠もないものがどんどんなくなっていくだろう、と考えていました。しかしトクホの申請にとてもお金と時間もかかるため、なかなかトクホ商品が増えませんでした。
そこで国はもう一段取得しやすい制度を作ろうということで、機能性表示食品を作りました。
機能性表示食品がたくさん増えれば、いわゆる健康食品はなくなるだろうと考え、今は国は機能性表示食品を一生懸命応援をしています。
トクホと機能性表示食品というのは、少なくとも効果があるという科学的根拠が明確です。ところがいわゆる健康食品というのは、そういった表示がありませんし、イメージだけで売っています。科学的根拠は、一切明かにしていません。つまり、効くのか効かないのかはもとより、安全なのかどうかもわかりません。それが、いわゆる健康食品といわれるものです。
ですので、薬屋さんに行くとあらゆる健康食品が並んでいますけれども、トクホマークや機能性表示食品というマークがあるものを選んだ方が絶対に安全であり、しかも効果は期待できる、ということになります。
■Part2:
「摂取する時や表示に関する注意点」
トクホや機能性表示食品は買っても大丈夫です。
しかしその表示がないものは買わない方がよいです。それは、安全性も効果も分からない、というそこのところが第1の大きなポイントです。
第2のポイントは、トクホにしろ機能性表示食品にしろ、血圧が高めの方や肥満の方等に、いろんな効能が書いてあります。自分にとってどれが必要なのかということはよくよく考えて自分に合うものを選ぶというのがとても大事なことなんです。さらに、薬もそうですしトクホや機能性食品もそうですけれども、誰にでも効くというわけではありません。よく効く人と効かない人がいますので、少し飲んでみて効かなかったら止めた方がいいです。それから、これは体質と関係するんですが、トクホや機能性食品でも副作用がでることがあります。ですので飲んで少しでもおかしかったらすぐ止める。そして保健所に、あるいは医師に相談をしたほうが良いです。
注意点はたくさんあるのですが、サプリというのは、飲み続けるとだんだん依存性ができてしまいます。1ヶ月飲んでいたのに突然1日だけやめると、なんか体調がおかしい等、気分的におかしくなることがあります。そのようにして、効き目があまりわからないのに、ズルズルと飲み続けてしまうことがあります。
ですのでズルズル飲み続けないで、1ヶ月ぐらいを目処にして効果がなければやめるということが大切です。一度やめてみて、1週間、2週間やめてみます。それで何もなければもうそれはやめてもいいと思います。やっぱり必要だったらまた飲めばいいと思います。ズルズル続けないということも大事なことだと思います。
結局はトクホにしろ機能性表示食品にしろ効能はあるんですけれども、それは薬のような明かな効能ではありません。
ですのでそれが自分に合う人と合わない人がいます。トクホとか機能性表示食品というマークがあれば、自分がどれをどんな機能性表示食品、トクホでどんな効能を選ぶのか、ということが大事だと考えます。
トクホ、機能性表示食品という表示があるということが大事であり、それさえあれば、中身は信用できるというふうに考えてよいと思います。
「病後に健康食品は摂っていいのか」
トクホとか機能性表示食品をどういう人が飲むべきかというのは、厚生労働省のホームページ に書いてあります。これは実は健康な成人です。病気の方は薬を飲んでください。
病人がトクホや機能性表示食品で病気を治そうと考えるのは間違いです、ということです。
それからお子様には飲まさないでください。トクホや機能性表示食品のテストっていうのは全部大人でやっています。
ですので子どもに効くかどうか、子どもに安全かどうかはテストしていません。
お子様には飲ませてはいけませんので、赤ちゃんにはとんでもないということになります。健康な大人が自分の健康を維持するために使ってください。これがトクホと機能性表示食品なんです。
病後の方が、自分の体力の回復に努めたいと思ったら、厚労省は、きちんとした食生活で回復してください、トクホや機能性表示食品でそれを期待するのは間違いです。というように言っています。
健康になって、さらに何か欲しければ健康食品を摂ってもいいですが、それで産後の疲労した身体が急に良くなるんだ、ということはないということです。
■Part3:
「海外の健康食品の安全性」
国によって安全性は変わってきます。
日本の機能性表示食品は、アメリカの制度の真似しています。アメリカは、FDA(Food and Drug Administration)という担当の省庁は、これは審査しません。
企業が自己責任で表示をしていいですよ、ただ、それはFDAが認めたものじゃありません、ということを書きます。そういう制度を日本は真似しています。
ですので論文を届ければOKにするという制度になっています。もし何かあったらすべて企業の責任です、ということになっているのです。
ネットで海外の健康食品を買う人がいますが、これは絶対やめた方がよいです。海外の健康食品に関する制度をよく理解しないで買ってると思います。実際に中国産の痩せるという健康食品で、肝機能障害をおこして亡くなった方までいますので、ネット経由で海外のものを買うのは大変リスクが高いということを覚えておいてください。
「健康食品の可能性」
高齢者も若い人も、健康に対する関心というのはどんどん高くなっています。
厚生労働省は、健康を保つためには正しい食生活、正しい生活習慣をきちんと守ってくださいと言っています。これが健康を守る最も大事なことです。
それに加えて健康食品がどうしても必要であるというのであれば、トクホか機能性表示食品を摂るということもあり得ることだと思います。
機能性表示食品やトクホには科学的に証明されている効能の他に、実はプラセボ効果というのがあります。
プラセボ効果というのは、これを飲むと絶対に健康になれると信じると、そのトクホや機能性表示食品が持っている効果以上の効果があるという現象です。
例えば膝の痛みを持ってる人がたくさんいるとします。薬理学的試験をキッチリやりますと、トクホや機能性表示食品でもかなり良くなることがあります。でもそれは、プラセボという全く効果が無いものしか入っていないものを飲ませてもかなり効果があります。そういったプラセボ効果というのもありますので、機能性表示食品やトクホというものは宣伝している通りの、あるいはそれよりも光画がある場合もあります。
ただ、これらは全てに効くわけではありません。痛みとか不安とか睡眠とか、その心理作用が働くものにはよく効きますが、例えば癌の薬の副作用は、心理作用でよくなりますが、癌自体が良くなることはありません、というように効かないものもたくさんあります。
ですので先ほど申し上げたように、自分が飲んで良く効いたらそれは使ってもいい、効かなければすぐやめた方がいい、ということは、プラセボ効果からも言えます。
第5回 筑波大学 産婦人科学 医学博士 佐藤 豊実先生
収録日:2018年5月26日
筑波大学 産婦人科学 医学博士 佐藤豊実先生が婦人科がんついて語ります。
Part1:「婦人科がんの治療の現状」
Part2:「卵巣がんについて」
Part3:「婦人科がんの遺伝的要因の検査方法」
Part4:「婦人科がんの今後の治療や患者さんへのアドバイス」
※動画左上のメニューボタンをクリックすると、再生する動画を選択することが出来ます。
各動画の要旨は以下になります。
■Part1:「婦人科がんの治療の現状」
現在急速に増えている婦人科がんが子宮体がんです。30年くらい前は子宮頸がんが9人に対して体がんが1人というような割合だったのですが、現在は年間の罹患者数は子宮体がんの方が多くなっており、頸がんの1.5倍くらいに子宮体がんが増えているという状況になっています。
子宮頸がんに関しては、若年の方が増えています。昔は60代後半~70代の方が多かったのですが、今は40歳前後の子宮頸がんの患者さんが非常に増えています。
全体の数としては、子宮がん検診等が始まった戦後以降、子宮頸がんは減ってきていましたが、1990年代くらいに底を打ち、少しずつ増えてきています。その増えてきているところが、若年層が非常に多くなっています。
卵巣がんでは、患者さんも30年前くらいまでは年間3000人くらいだったのですが、現在では1万人に届くかそろそろ超えてくるというような状況になってます。その原因としては、昔と比べて日本人の女性のライフサイクルに変化がでてきているということも、一つの原因になっているだろうと思います。
子宮体がんについてですが、子宮体がんは初期から不正出血という症状があるので、その時点で病院に来て下されば、早期のうちに見つけることができます。手術を行うことで、がんによって命を落とす確率は非常に低くなっています。ただ、不正出血はあるけれども、「更年期ではないか」というように、自己診断したり人から言われたりして病院に来る時期が遅れてしまうと、がんが進行してしまいます。そうなると、手術や抗がん剤の治療、場合によっては放射線療法など組み合わせて治療することになります。そのようなことにならないように、症状があったら早く来ていただきたいと思います。
子宮頸がんの場合の症状としては、不正出血やおりものが増えたりしますが、子宮頸がんの場合は、そういう症状がでてきた段階ではすでにがんが進行してしまっているということがあります。子宮頸がんの早期発見は、子宮がん検診しかありませんのでしっかり子宮がん検診を受けていただきたいと思います。
子宮頸がんになってしまった場合でも早期であれば手術、もしくは手術プラス放射線療法で、半分よりも早いうちであれば治る確率が高いとされています。ただ、手術ができないくらいに進んでしまいますと、放射線治療が必要になります。それでも治る確率は半々くらいと思います。
放射線治療は、昔と比べると安全性が高まっていますが、5年後10年後、15年後20年後というところで、副作用として、腟と膀胱とか、腟と腸の方とですね 穴が開いて通じてしまうというようなことも起きてきますので、やはり検診で早くみつけてしっかり標準的な治療で治す、というのが大事だろうと思います。
問題は卵巣がんで、卵巣がんは欧米だと「サイレントキラー」という呼ばれ方をしています。つまり、症状がなかなか出ないんがんで、気づいた時にはもう3、4期と病気が進んでしまった状態でみつかることが多いがんです。
筑波大だとだいたい3、4期の方が60%くらいおります。この状態の場合、手術と抗がん剤の組み合わせでがん状態であっても普通の生活をしていただく、というところしか狙えない患者さんも出て参ります。
もちろん、卵巣がんにもいろいろな状態があって、お腹がすごく膨れてくるくらい大きな腫瘍になっても、状態によっては粘液性がん等であれば、 1期であることもありますので、卵巣がんになったら全部だめだということでは決してありません。
各々の自治体では検診の間隔等を決めて実施しておりますので、そのようなお知らせがあった場合にはぜひ受けていただきたいと思います。かつては、細胞診という検査で検診が行われており、1年に1回というように推奨されていました。しかし最近はこれに子宮頸がんの原因のウイルス、ヒトパピローマウイルス(HPV)に感染しているかどうかのチェックも併せて、細胞診とウイルスのチェックを行い、問題なければ、2年に一度とか、3年に一度とか間隔で良いのではないかと考えられています。海外ではもう間隔を延ばしてやっているところが多くなっています。日本もだんだん多くなってくると思います
■Part2:「卵巣がんについて」
卵巣がんに対しては、検診が有効かどうかっていう臨床試験も行われたのですが、結局、有効だという結論には至りませんでした。漿液性がんというタイプが一番多いのですが、これはともすると、1期2期という早期の状態がなくていきなりお腹の中で、同時多発的に出現するという可能性も示されています。
信州大学での研究では、卵巣がんになった方にいつ産婦人科で超音波とかの検査を受けたかを調べると、3ヶ月前には何でもなかったという人が多い。ところが、その3ヶ月後には3、4期という状態になっている。このように早期発見は非常に難しい、あるいはもともとできないのかもしれません。ただ、粘液性がんや明細胞がんは、成長が大きくなっても1期のことが多いので、どうもお腹が出てきたかな、太ったのかな、と感じたなら産婦人科に来ていただければと思います。
卵巣がんの原因ですが、明らかにこれが悪いんだという、肺がんにおける「タバコ」のようなものはわかっていません。 ただ、最近注目されているのは遺伝性のものがあります。遺伝的な素因を持っている方は、生涯罹患率はたぶん60~70%くらいでありますので、何らかの対応が必要となります。
月経排卵が卵巣がんを増やしている可能性もあります。昔は早めに結婚して、たくさん子どもを産んでおりましたので、妊娠中は月経はありませんので、排卵もありません。授乳中も基本的には、排卵もなく月経もありません。そうすると、卵巣がんというのは、一つの説として、卵が卵巣から飛び出す時に卵巣の一番表面の膜を破って飛び出していくと言われており、この機械的な刺激が多ければ多いほど卵巣がんになりやすい、という説があるのです。つまり排卵が多いほど卵巣がんになりやすい。
今は、産む子どもの数が減っているので、その分、排卵している期間が長くなリ、卵巣がんの原因じゃないかと言われています。
もう一つは、子宮内膜症という病気があり、これは月経の時に子宮の内側の膜から出血するのですが、これが子宮以外の場所にできた場合、これを子宮内膜症といいます。 卵巣にもそれができることがあって卵巣の子宮内膜症になると、月経のたびに卵巣の中で出血していきますから、卵巣が腫れていきます。これは良性なので良いのですが、これががん化することがあります。ただ、先ほどと同じ理屈で、妊娠中は月経が来ませんし、授乳中も基本的には月経が来ないので、月経がない期間が長ければ、子宮内膜症になってても自然に退縮していきやすいし、がんにもなりにくいのです。これがずっと月経がある状態だと、子宮内、卵巣の中にも出血があって一ヶ月に一度くらい常にあって、その出血が毎月毎月ずっとある期間が長いということで、そのうちにがんに変化していく、ということが考えられています。
■Part3:「婦人科がんの遺伝的要因の検査方法」
自分の家系内にどんながんの方がいるのかいないのか、というのを、確認なさるといいと思います。外来で患者さんにご家族でがんの方いらっしゃいますか、と必ず聞くのですが、9 割ぐらいの方はいませんと、おしゃいます。多分、一緒に住んでいるご家族で考えてると思われますが、お爺さんお婆さん叔父さん叔母さん従兄さん、と尋ねると、「あ、いました」と言って一人二人出てきます。現在は2人に1人ががんになっている時代ですので、可能ならば、曾お爺さん曾お婆さんの範囲からお爺さんお婆さんのご兄弟の範囲、姪御さん甥御さん従兄ぐらいのところまで調べてみるといいと思います。
ご自身が卵巣がんになった場合は、遺伝性の可能性があると思われます。アメリカでのガイドラインでは、本人が卵巣がんだったら遺伝子検査をすすめるということにはなっています。日本ではまだそこまでできていませんが、親族にもう一人卵巣がんがいるのであれば、乳がんにもなりやすい可能性があります。
男性の場合、前立腺がんが遺伝の影響を受け易いと言われています。また、肝臓がんも出やすいと言われていますので、そのようながんに罹患された方がいる場合は遺伝子検査を考えても良いと思います。親から子に伝わる確率は50%ですので、全ての方に伝わるわけではありませんので、ご自分が卵巣がんになった場合で、親族にもいらっしゃるのであれば、親族の方に調べていただくのがよいと思います。それで、病的な変異があった場合はご自分も検査を考えてみると良いと思います。検査できるところには、必ずカウンセリングを受けられる部門がありますので、そこでよく話を聞いていただいて、受けていただくのがよいと思います。
■Part4:「婦人科がんの今後の治療や患者さんへのアドバイス」
子宮がんの方のための新しいおクスリが出るめどは今のところ立っていないというのが現状です。
卵巣がんのキードラッグ、治療に使われる一番大事なお薬は、プラチナ製剤というものがありますが、これが効いている患者さんには「PARP阻害剤」というお薬がありまして、これが先の2018年4月18日から保険を使って処方することができるようになっています。 これには非常に期待していまして、臨床試験によるとプラチナ製剤を含む抗がん剤の治療をやって有効だった方に、その抗がん剤が終わった後、メンテナンスのように、服用を毎日していただきます。
試験では症状が悪くなったらそこで終了、ということになるんですが、悪くならないで5年6年7年と飲んでいる方が10%くらいいらっしゃいます。つまり、もしかすると本来治らないだろうと思われていたがんが、たとえ10%の確率であったとしても治っている人がいるかもしれない、ということになります。
この薬が再発の卵巣がんの方にも使えるようになりましたので、機会があれば使っていただきたいと考えております。患者さんの辛い症状も、従来の抗がん剤とくらべると非常に少ない印象があって、患者さんの生活の質、QOLを高めてくれていることも間違いないだろうと考えています。
卵巣がんに関しては免疫チェックポイント阻害剤というものがあります。これの治験がいくつかあり、結果がそう遠くない将来出ると思われますので、これにも期待しています。免疫チェックポイント阻害剤も、再発卵巣がんの方が治る確率が非常に低かったのですが、治してくれる可能性もある、と思って期待しています。
他に、薬ではないですが、子宮体がんや子宮頸がんに関してはロボット手術ができるようになっていくのではないかと 考えています。子宮体がんは既に保険適用になってできるようになっていますが、頸がんに関してもなっていくのではないかと思います。今年(2018年)の4月から産婦人科の領域でもロボット手術が保険適用になりましたのでどんどん実施する施設が増えていくと思われます。
ロボットの場合は、患者さんの術後が非常に楽ですので開腹手術、腹腔鏡下の手術、そしてロボット支援下の手術、というのをうまく使い分けていくと、患者さんの傷の大きさや、術後の痛みとか、 質の高い患者さんが楽な医療を提供できるのではないかと考えています。
大切な点の1つ目は、いわゆるAYA世代の妊娠を考えられる世代の方の子宮体がんも頸がんも卵巣がんも、条件はありますけれどもがんになっても、赤ちゃんを産む力を残した治療、という選択肢がああることです。非常に進んでる方には難しいですが、そういう道がありますので、がんになった=もう子どもは産めないんだ、ということではありませんので、その辺の知識が十分にある婦人科腫瘍専門医の方に、もし子どもを産みたいんだけどがんになってしまうという場合には、婦人科腫瘍専門医がいるところでその医師からの説明を聞いてもらえればよいかと思います。
2つ目は再発なさった患者さんのことです。卵巣がんの患者さんでも、頸がんの患者さんでも体がんの患者さんでも、再発してから10年間くらい、再発しては例えば手術で取るとか、再発したんだけれども腫瘍はあるんだけれども、とりあえずすぐに手をつけるのではなくて、ある程度の大きさになったら、そこだけ放射線をかける、というような工夫をしながら普通に生活をなさっている方がいらっしゃいます。その方達は、今度新しいお薬が出たので、またそれでチャンスが出てくる。
治療はなかなか辛いところがありますが、その辛さはたとえ医師であっても本当のところはわかりません。だとしても、受けて効果があるのであれば断続的でも構いませんから医師とチームになって、つないでいく。次のチャンス、次のチャンスと、必ず出てくるので、ぜひ諦めずにもうすでに頑張っていらっしゃる患者さんに、さらに言うのは酷なのかもしれませんが、もうひと頑張りしていただけたら嬉しいな、と思います。
第4回 千葉労災病院 勤労者脊椎・腰痛センターセンター長 山縣正庸先生
収録日:2017年12月6日
千葉労災病院 勤労者脊椎・腰痛センターセンター長 山縣正庸先生が腰痛の病態と治療の最前線について語ります。
Part1:「腰痛とその原因」
Part2:「変わってきた腰痛の概念」
Part3:「腰痛治療と予防について」
Part4:「腰痛対策の基本」
※動画左上のメニューボタンをクリックすると、再生する動画を選択することが出来ます。
各動画の要旨は以下になります。
■Part1:「腰痛とその原因」
腰痛というのは一般的に広い概念であり、単なる腰痛だけではなく下肢痛を伴っている腰痛もあります。3年に一度、国民衛生の動向という有訴率(自覚症状のある人の割合)が厚生労働省から発表されています。それによると、腰痛・肩こりはいつもトップに入って来ており、男性女性とも腰痛は非常に有訴率の高い疾患ということになっています。
どうして腰痛が問題になるかというと、例えばアフリカの遺跡で発掘された人骨をみてみると、狩猟をやっていた時代にはあまり腰痛の人はいません。エジプトとか農耕民族になってくるとだんだん屈んでやる仕事が多くなって、腰椎が変形している遺骨がみつかっています。人間は歴史とともに腰痛を背負ってきたといわれています。2001年に、ニューイングランドジャーナルという雑誌が非常にショッキングなデータを発表しました。アメリカの一般家庭医の先生が腰痛の患者さんを調べたところ、原因が特定できない腰痛が85%もあるという結果がでました。その先生は、原因が特定できない腰痛を「非特異性腰痛」と名をつけて世界に発表しました。それが契機になり、様々な画像検査が進んだとも考えられます。現在はMRIやCT等の画像診断も進歩しまして、今では非特異性腰痛のだいたい7割くらいは特定できる状況になりました。原因として多いのは、筋肉や筋膜の痛み、椎間板の痛み、椎間関節の痛み、仙腸関節といって骨盤よりちょっと下のところにある関節の痛みが、非特異性腰痛として分類されてしまっていましたが、現在では画像診断でそれらがわかるようになってきたと考えられます。一般的に腰痛の原因は部位的に考えられる場合が多いです。
脊椎由来の腰痛、神経由来の腰痛、内臓由来の腰痛、それから血管も腰痛の原因になります。さらに、心因性といって心理社会的な意味、自分の心の状態が原因の腰痛というのも考えられていて、私たちは患者さんを診る時に、この人の腰痛はどこからきているのかというのをこの5つの中から選択して原因を探っています。脊椎由来の腰痛が圧倒的に多いのですが、椎間関節(動きを制御しているところ)、椎間板(体重を支える一番もとになっているところ)、椎体、神経根といって後ろに出ている神経による腰痛もあります。これらを考えて、どの部分でどの組織が傷害されているか、傷ついているかを考えて治療しています。腰痛を起こす疾患というのもいくつかあります。よく知られている腰椎椎間板ヘルニア、すべり症、最近では、腰部脊柱管狭さく症という病気があります。お年寄りになってくると、骨粗しょう症、それの圧迫骨折による痛み、変形性脊椎症、筋・筋膜性腰痛、等様々ありますが、一般的にこれらの病名が、皆さんが整形外科を受診した時につけられるものです。ただしその中で、転移性腫瘍、化膿性脊椎炎、結核性脊椎炎、馬尾腫瘍、そういった腫瘍や感染といったものも腰痛の原因になるので、専門の医師が注意をして診なければならない点です。
2012年に腰痛ガイドラインが策定されました。それによると、重篤な脊椎疾患を疑うものは「red flags」といわれてまして、発症年齢が20歳以下か55歳以上、時間や活動性に関係なく腰痛が出てしまう場合はred flagsです。それから、胸部痛など他の部位の痛みを伴うもの、それもred flagsになります。がんやステロイドの治療をしている、HIV(エイズ)の治療をしている、栄養不良、体重減少が非常に急速に進んだ場合もred flagsといわれています。さらに、ヘルニアのように1本の神経根の症状だったらいいのですが広範囲に神経症状が出ているような場合もred flagsで、私たちが対応しなければならない疾患となります。
発熱を伴う腰痛も注意が必要です。熱を伴っている場合には、化膿性脊椎炎等を考えなければいけないので発熱も重要なサインとなります。お年寄りの方の姿勢がだんだん曲がってきて腰痛になる、成人脊柱変形というのも非常に問題になっていまして、以前はお年寄りだから仕方がないとされていましたが、それをまっすぐにしてあげるとクオリティ・オブ・ライフ(生活の質:QOL)があがるということで、限られた施設ではありますが、成人脊柱変形に対しての腰痛治療を行うという新しい治療法が出てきています。
■Part2:「変わってきた腰痛の概念」
腰痛と生活習慣、これは運動不足と関係があるといわれていてこれはガイドラインにエビデンスとして示されています。
腰痛と喫煙も関連があり、喫煙者の方は腰痛がなかなか治りにくい、発症も多いといわれています。意外と思われるかもしれませんが、腰痛と体重、BMI(Body Mass Index)には関係がないというデータが出ていて、太っているから腰痛がある、痩せすぎて腰痛になる、ということはないと論文で示されています。腰痛は、繰り返し発症するということが特徴です。腰痛の原因にもよるのですが、腰痛の発症と遷延には心理社会的な因子が関係しているといわれていて、腰痛になった人がどういう社会的な立場にあるか、心理状態であるかということが発症の原因になったり、遷延化するということがいわれています。特に精神的な要因として、うつ状態になりやすい人は病態が遷延化し、発症もしやすいといわれています。福島県立医科大学の菊地教授が、どこか傷害されてそこから痛みの物質が出てきて痛みと認識する、その痛みだけではなくて心理的、社会的な概念も取り入れて「生物・心理・社会疼痛症候群」バイオ・サイコ・ソーシャル・ペインシンドローム(Bio-psycho-social pain syndrome)という考え方を発表しました。
社会の状態やその人の心理状態が疼痛の状態をコントロールしている、というようなことを考慮して、腰痛治療の時にその人だけを治すのではなくて、その人のバックグラウンドをみて、治していかなくてはならないというように考えられています。
■Part3:「腰痛治療と予防について」
腰痛治療について安静は必要か?単純な疑問だと思います。
近年、安静は必ずしも有効な治療法とはいえないといわれています。安静にしてたグループと我慢して動かしたグループとをみますと、痛みに応じて活動性を維持した場合の方がより疼痛を軽減することができるということが、データとして裏付けされており、できるだけ動かすことが推奨されています。私も外来で、少し動けるようになったんだから寝てる間もベッドの上で手足を動かしてください、というようにとにかく動かすということを患者さんに勧めています。腰痛で整形外科医を訪れるとお薬をもらったりしますが、患者さんによっては「効かないですよ」と言う方もおります。しかし、実際にはだいたいの人に効果がみられます。しかし、その人が目的とするところまでは疼痛がとれてない、ということがほとんどだと思います。腰痛に対する薬物治療の臨床研究も進んでおり、今では単なる消炎鎮痛剤だけではなくて、抗うつ剤や抗てんかん薬、痛みをコントロールするためのオピオイド等の医療用麻薬も使えるようになっており、疼痛をコントロールできる状況になっております。コルセットも腰痛に対する機能改善には有効でありますが、ただ、ずっと付けていてよいかというと、それも問題で、あるところでは動かしながら治していくということが必要だと考えられます。椎間板や軟骨には血管が通っておりません。そのためじっとしていると栄養が届きません。動かして初めて軟骨は関節液が流れます。椎間板も圧力を加えて取り除くということを繰り返すことで、椎間板の中に栄養剤、栄養物質が浸透していくといわれているので、じっとしていると治療が進みません。そういったことから、腰痛や運動器については、動かしながら治すということが治療の基本になっています。ガイドラインでも、亜急性腰痛の発症から1ヶ月~3ヶ月ぐらいまでは、限定的ですが運動はやった方が良いといわれています。もう少し痛みがあって動けなくなっているとか、廃用性とかになっている、3ヶ月以上ずっと腰痛を続けている人は、多少痛くても運動した方がより腰痛が早く、効率的に治るということがいわれていて、特に慢性腰痛に対しては運動療法がいいといわれています。ただ、よく質問されるのですが、どういう運動がいいのかと。よく腹筋を鍛えましょうとか言うんですが、それだけではダメなので運動の種類によって、例えば腹筋がいいか伸展筋がいいかというのは、いろいろ学会で問題になるんですが、どれだけを鍛えればいいのかというのは、今のところエビデンスはないのです。だから総合的に運動をすることがよくて、私は、わりとお年寄りの方には散歩というか屋外に出て歩いてくるということを勧めています。腰痛にならないためにはどうしたらいいか?ということについてですが、つまり、腰痛の予防は可能かということなんですが、この薬を飲んでたら、この食事をしてたら腰痛にならないということはなく、やはり運動療法は腰痛発症の予防に有効であるということも論文化されていて、普段から体を動かして腰痛を起こさないような対策をとっておく、ということが重要だと思います。それから、仕事をする時に、例えば介護の人とか多いんですけども、前傾姿勢で体軸に力がかかってしまうような時にはコルセットをすると椎間板の内圧がかからないので、それは非常に有効です。だから予防的にコルセットを使うというのも有効な予防法です。
■Part4:「腰痛対策の基本」
腰痛というものは非常に漠然としていて怖いのですが、病態に応じて治療が可能ですから、ちゃんと知って、それに対する対策をとるということが重要です。薬物治療もいろんな薬物が開発されてきているので、今までの単なる消炎鎮痛剤だけではない、いろんな方法・薬物があるので、近年治療法も大きく変わってきており、以前のようにただ痛み止めを出すというような方法ではなくなっています。慢性的な腰痛の場合、長期間お薬を服用されてしまう方がいますが、有効とされているのはやっぱり運動です。セラピストがちゃんとついて、その人にあった運動を勧めていくということが今推奨されています。痛みというものは身体に警鐘を鳴らしているわけですので、本来、生理的に必要なものなのです。だから、痛みを感じるような作業姿勢や運動がいけないわけで、それを工夫することで腰痛を感じない生活をすることも可能なはずです。腰痛そのものは、「red flags」でなければ悪性の病態ではないので、それと上手くつきあい、なるべく腰痛を感じないような生活を送れるようになることが一番良いのです。
最新の治療法についてですが、固定手術だとかいろんな手術法が進歩しており、内視鏡で手術をしたり低侵襲手術としての固定手術といった新しい機械が開発されてきているので、今後、進歩していく分野だと思われます。
腰痛というのは非常に苦しい、患者さんのQOLを下げてしまうものですが、決してあきらめないで、自分のかかりつけの先生を見つけてその先生と一緒に腰痛について対策をたてていく、ということで、少なくとも、苦しんで動けなくなってしまうというのではなく、自分で歩ける状態をいつまでも続けられるかなと思います。
どうぞ、良い主治医さんを見つけてくれるといいと思います。
第3回 HAB研究機構副理事長 寺岡慧
収録日:2017年6月3日
HAB研究機構副理事長 寺岡慧がヒト組織を研究に供するためのわが国の対応、外科手術の現場に協力を求めるための方策、HABの今後について語ります。
Part1:「ヒト組織を研究に供するためのわが国の対応について」
Part2:「外科手術の現場に協力を求めるための方策について」
Part3:「今後のHABについて」
※動画左上のメニューボタンをクリックすると、再生する動画を選択することが出来ます。
各動画の要旨は以下になります。
■Part1:「ヒト組織を研究に供するためのわが国の対応について」
死体解剖保存法の17条と18条に死後、摘出した標本の研究や教育用に利用することに関する規定が書かれています。
それには遺族の承諾というのが前提であるということと、承諾がある場合にはそれを標本として保存することができるということが書いてありますが、研究に関しては詳しい規定がありません。
1997年に、臓器の移植に関する法律ができ、9条に死体から摘出した臓器を移植術に使わなかった場合には厚生労働省令に規定する方法によって処理しなければいけない、と書いてあります。その厚生労働省令の第4条には、移植術に使わなかった場合には焼却して処理しなければいけないということが書いてあります。
つまり、臓器として移植用の臓器として提供されたものが移植に使われなかった場合に、それを研究に転用することは現在ではできないということになっています。
他方、亡くなられた方からの組織の提供に関しましては特に法律がありません。そのため、臓器の移植に関する法律には運用に関する指針、ガイドラインがあり、第14条に組織の移植に関する取り扱いが書いてあります。
本人または遺族の承諾があること、それが社会的・医学的見地から適正であれば本人の生前の意思、あるいは遺族の書面による承諾をもって組織を摘出してよいとされています。この場合には組織を移植に使わなかった場合には特段の規定はありません。
したがって、移植用の組織として提供された組織に関しては、使わなかった場合には遺族の書面による承諾があれば研究用に転用しても問題ないと解釈できます。
これが現在の我が国の対応です。
臓器の場合は厚生労働省令の規定により焼却しなければいけない、ということになっておりますが、本人または遺族の書面による承諾がある場合には研究に転用してかまわないというように厚生労働省令の改正を行えば、研究に転用することができるということになります。
すでにお話ししましたように組織は、現在でも既に研究に転用ができます。
本来、臓器を提供される場合にどういう動機でご遺族が提供されるか、ということになりますが、本人の意思を活かしたい、あるいは、本人の意思を尊重して、何らかの形で社会に役立てたい、社会貢献をさせたいというご遺族の希望、さらに医学の発展のために、あるいは他の病気の患者さんのために役立てたいというようなお気持ちが大きな動機になっています。すなわちご本人の意思やご遺族のご希望・要望を原点に立ち返って活かすために、移植に使えなかったら、それを焼却してしまうということではなく、多くの患者さんの治療に役立てるような研究にも用いることができるというようにすべきだと、そのような時代が来ているのではないかと考えております。
■Part2:「外科手術の現場に協力を求めるための方策について」
手術で摘出された標本には、法的な特段の規定がありません。実際には手術で摘出された組織は様々な検査に使われております。これは、研究というよりもその人の治療に関連した検査ということになると思います。ただし、本人以外の治療や成果の応用ということになると、それは検査ではなく研究的な意味をもってきます。
そういったことも含めて、今の段階でも手術で摘出された標本をご本人の承諾があれば、それを研究に転用するということが可能です。手術で摘出されたものが誰に帰属するのかという問題がありますが、通常は患者さんご本人に帰属すると考えられます。ですので、その方の承諾を得られれば、研究に使うことは可能となります。
しかし、あくまで社会的にも医学的にも正当であるという範囲内で行われることになると思います。これに関しましては今後も徐々に広がっていくのではないかと考えています。
■Part3:「今後のHABについて」
現在のHABは外国から輸入した組織や細胞を研究に用いるための仲介役を果たしています。今後の我が国における医学的な研究のための重要な橋渡しの役割を果たしていると思います。しかし問題は、日本人の組織と外国の方の組織とは違うことです。遺伝子等、様々な点が異なっています。日本人のための治療を研究するためには、もちろん外国からの組織・細胞も必要ですが、それに加えて日本の方々からの提供も必要なのではないかと考えます。
そのためには、3つの流れがあります。一つは、バイオバンクです。手術で摘出された標本を、ご本人の承諾を得て研究に転用していくという考え方です。すでにバイオバンクは日本では数カ所運用されております。
もう一つは、臓器の移植のために摘出された臓器を移植に使えなかった場合に、研究に転用できるようにしてはどうかという考え方です。これは、臓器の移植に関する法律の施行規則(厚生労働省令)を改訂して、移植に使われなかった場合には研究に用いることができると改正すれば、今後可能になります。
さらにもう一つの方法としては組織移植のために提供された組織の転用があります。組織の移植用に摘出された組織を研究に転用することは今でも行われていますが、臓器の移植に関する法律が改正されて以来、組織の提供が減少しています。例えば皮膚の移植は非常に重要で、重傷のやけど(熱傷)の患者さんの救命率を上げるには不可欠です。それが現在、提供が少なくて非常に困っているという状況で、皮膚をはじめとした組織の提供を今後増やしていかなければいけません。
現在、臓器移植ネットワークで臓器の提供に関する手続きや斡旋が行われていますが、組織は臓器とは別のコーディネイターにより行われています。このように臓器と組織で分かれているのは日本だけで、諸外国では、組織も臓器も全部、一体化して行っております。今後は日本臓器移植ネットワークで臓器だけではなく、組織の提供についても一体的にやっていただいて、組織の提供を増やしていただきたいと考えます。そうすれば、移植に使えなかった場合に、研究に用いて多くの患者さんの治療のために役立てることができるようになると思います。
厚生労働省令を改正して、移植用の臓器の研究への転用が可能になれば、移植に使用できない場合は、亡くなられた方から善意で提供された臓器・組織を、病気と闘っている多くの患者さんのための研究に役立てていくという、本来の尊い善意の意思を活かせることにもなります。
上記のように組織の研究への転用には三つの流れがあり、これらの流れをどういうふうに調整し、推進していくかということが重要だと思います。HABは上記の三つの流れをネットワーク化してまとめるような立場でやっていったら良いのではないかと考えております。
※ヒト試料を研究に転用する場合は本人または家族(遺族を含む)の書面による承諾を得ています。
第2回 東海大学医学部消化器外科 中郡聡夫先生
収録日:2017年6月3日
東海大学医学部消化器外科 中郡聡夫先生が膵臓がん治療の現状と将来について語ります。
3部構成になっており、それぞれ以下のテーマで語っております。
Part1:「膵臓がん患者はなぜ増えてきているのか」
Part2:「膵臓がん治療の現状-なぜ治療が難しく、予後が悪いのか」
Part3:「膵がん治療の将来展望」
※動画左上のメニューボタンをクリックすると、再生する動画を選択することが出来ます。
各動画の要旨は以下になります。
■Part1:「膵臓がん患者はなぜ増えてきているのか」
膵臓がんの患者さんは増えています。日本では年間1000人ぐらい、死亡数が毎年増えています。
2017年は日本では3万4000人ぐらいの死亡数が予測されています。
増えている原因ですが、ハッキリとわかっていません。高齢化が一つの原因としてありますが、根本的な理由はわかっていません。糖尿病の患者さんが増えていることは、直接的では無いのですが関連しているのではないかと思っています。
しかし、遺伝子の因果関係など、直接的な膵臓がんの原因はあまりわかっていないというのが実情です。
■Part2:「膵臓がん治療の現状-なぜ治療が難しく、予後が悪いのか」
膵臓がんは非常に治療が難しい病気といわれています。
難しい一つの理由に診断の難しさがあります。つまり見つけにくいと言うことです。
膵臓の場所が胃の裏側の奥にあるため、症状が出にくく、症状が出た段階ではかなり進行した状態になっています。
見つかった段階で手術ができるのは全体の2割ぐらいになります。残りの8割は見つかった段階で手術ができないくらいに拡がっているという状態です。
もう一つの治療の難しい理由は、膵臓がんには抗がん剤が効きにくいというものがあります。
最近は徐々に膵臓がんに効く抗がん剤が開発されてきていますので、将来的には希望を持てる状況にはありますが、抵抗性の強いがんといえます。
それから、三番目の理由は手術後の再発率の高さです。
胃がんや大腸がんなどと違い、手術で治る人は4人に1人で、残りの3人は再発してしまいます。
その理由は、膵臓の周りにゲリラみたいにがん細胞が残ってしまっていたり、肺や肝臓などの遠いところに小さな転移が起こったりするためです。
そういった理由から、がんの中でも肺がんと膵臓がんが治療が難しいがんということになっています。
ただ、先ほども述べたように新しい抗がん剤が出てきており、5年生存率も2005年ぐらいは10~15%ぐらいでしたが、現在は10%ぐらい上乗せされています。
最近はさらに良い成績も出てきておりますので、今後は期待できると思います。
■Part3:「膵がん治療の将来展望」
今一番期待されている治療法は、化学療法です。
フォルフィリノックスといって4種類の抗がん剤を集めて投与する方法やゲムシタビンとナブ・パクリタキセルという2剤を併用投与する治療法等、抗がん剤を複合的に併用して投与する新しい治療法が進歩してきており、治療成績が非常に改善しています。
手術できないような患者さんでも抗がん剤治療によって腫瘍が縮小し、手術できるようになります。また、術後の患者さんに使うことで、非常に長く生きていけるようになります。
最近はこのように治療法が進歩しており、手術と化学療法を組み合わせる手法が非常に期待できると考えております。
第1回 HAB研究機構理事長 深尾立
収録日:2017年4月12日
HAB研究機構理事長 深尾立がHAB研究機構のこれまで、現在、今後について語ります。
3部構成になっており、それぞれ以下のテーマで語っております。
Part1:「これまでのHABのあゆみについて」
Part2:「現在のHABの取組や活動について」
Part3:「今後のHABについて」
※動画左上のメニューボタンをクリックすると、再生する動画を選択することが出来ます。
各動画の要旨は以下になります。
■Part1:「これまでのHABのあゆみについて」
従来、人に使う薬の薬物動態を調べるために動物の細胞や動物実験を行って、薬理効果や副作用の有無などを調べていました。しかしそれでは思わぬ副作用が出たり、複数の薬の相互作用による副作用が出たりすることがわかってきました。
そこで、ヒトの組織を使って薬物動態研究が出来ないかと世界的に考えられるようになりました。
1990年のはじめぐらいから世界的にそのようなことが検討され、欧米では当局からガイドラインが作成されました。
日本でも同時期にヒト組織を使用した研究の必要性が叫ばれるようになり、産官学の方々が集まって検討が始まりました。そうした経緯を経て、1994年にHAB研究機構の最初の組織が生まれました。
日本ではまだ日本人のヒト組織を手に入れることは難しいだろうと考え、アメリカから提供を受けることを検討しました。アメリカでは1980年ぐらいからNDRIという組織が作られ、臓器移植に提供された方の様々な組織をいただいて、全米の研究機関に配布するという活動を行っておりました。そこでHABでは、NDRIと話し合い、一定の条件を満たした場合にヒト組織の提供を受けられるという関係を構築しました。
■Part2:「現在のHABの取組や活動について」
日本人の薬物動態を調べるためには、やはり日本人のヒト組織を使用して研究をする必要があります。
まずは、臓器移植に提供された臓器を研究用の試料として利用することが可能になる法的・倫理的検討を行いました。
そのためにHABではまず、薬学学会や医学学会に対してヒト組織を使用した研究の重要性を理解してもらうために学術年会と称した学会を年1回開催することにしました。
さらに、一般市民の方の理解も大変重要ということから、市民シンポジウムという活動も開催しております。
また、ニュースレターや市民新聞等の情報発信活動も行っております。
このような活動を通じて、日本人の臓器移植用に提供されたヒト組織を研究に活用できるような環境作りに尽力しています。
■Part3:「今後のHABについて」
日本人のヒト組織を合法的に倫理的に問題のまない形で提供できる社会にしていくことが今後のHABの一番の目的です。そのためにはまず、臓器移植用の臓器が使えなかった場合には研究用に使える環境作りがと必要と考えております。
ヒト組織を研究に使用することで、新しい薬の開発、発展に役立つということを多くの人に知っていただき、納得できるようにすることが大切だとHABでは考えています。